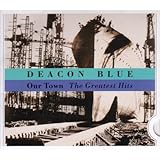彼らのロンドンレコード移籍一枚目のアルバム。ファクトリーの時代とは違い、スリーブは何所と無く、アメリカンチックで、自他とも認めるダサい品物。一曲目の「Regret」は、英米でスマッシュヒット(これも死語に近いか?(笑))あまりにも、この一曲目がポップで、完成度が高い為、他の曲がおまけのように思える。因みにこの頃までは、バーナードサムナーの人間ビール樽は存在しておらず。ナイスガイで、ヨットを乗り回すと公言していた時代だ。(笑)今は、、、
スコットランドが生んだ旅情詩人、リッキーロスがフロントマンのディーコンブルーのベスト版。「I'll Never Fall in Love Again」、「Real Gone Kid」などのヒット曲を収録。個人的に、「Love and Regret」は三十路には染みる一曲である。(笑)バンドは一時解散。1999年に突如再結成。2000年のアルバム、「Walking Back Home」へと繋がる。現在、地味に活動中。
ロック魂の男を虜にしてしまう色気を備え持つ、パッツィ・ケンジットが紅一点のバンド、エイスワンダーの所謂、ベストアルバム的な品物。ベースは、「Fearless」からの曲が殆どで、最後に彼女らの、スマッシュヒット、「Stay with me」が追加収録されている。あの当時、ストックエイトキンウォーターマンが全盛期で、もろそれ系の音楽。その当時、売れっ子だった、ペットショップボーイズも、「I'm not scared」邦楽タイトル「モンマルトルの森」で参加しております。オウェーシスのボーカル、リアムギャラガーとの結婚生活は終焉を迎えたが、最近はソープオペラで活躍し、シングルマザーとして、子供のミルク代を稼いでいる御様子です。(笑)
The La'sのメンバーだった、ジョンパワーが結成したバンドのデビューアルバム。ラーズ時代のポップチューンは健在で、このアルバムから、「Fine time」、「Walk away」などのヒットも生まれた。全体的に、新しい変化、希望の歌詞が頻繁に登場し。ジョンパワーのラーズ時代の邪念から開放されたいと言う気持ちが伝わってくる。最近、突如ラーズは再結成され、夏のフェスティバルに頻繁に登場した。しかし、その後はどうなるか、私達以上に、彼等も知らないだろう。(笑)

Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?
- アーティスト: The Cranberries
- 出版社/メーカー: Mercury
- 発売日: 1993/04/20
- メディア: CD
アイルランドが生んだ歌姫、ドロレス・オリオーダンが紅一点のバンド、クランベリーズのファーストアルバム。彼女等の最初の商業的ヒットは、アメリカMTVの猛プッシュから生まれ、そこから英国へと波及効果を生む形となった。このアルバムからは、「Dreams」、「Linger」などのヒットが生まれている。全体的に、「Dreams」の商業音楽としての使いやすさとは、一転して、このアルバムの感じは、暗い。「Linger」は、ドロレスのファーストキスに対しての心の葛藤を詩にしたと言われているが、後の、北アイルランド紛争「The trouble」について書いた、「Zombie」など、政治的な詩にも挑戦している。最近、彼女等は、一時解散を宣言した。
ベルギー代表GKさんの、「今度の予選で、皆で団結して、奴をボコボコにやってやる」と言う、発言に対して、ポルトガルサッカー協会が、UEFAにことの詳細を調査することを依頼。奴とは、そう、クリスティアーノ・ロナウドくんです。(笑)
Web 2.0って言う、ネットの新しい接し方と言える概念は、私的財産を危険にさらす可能性が私的されて、久しいが。この概念は、情報の共有と言う、理想的な考え方から生まれた物で、ガチガチに情報と言うある意味甘みのあるソースに、大金をかけてビジネスをやってきた、大型メディアには、昨今脅威であるようだ。これは、大型メディア指導でやって来た、情報の操作を、受け手の私達に開放された、ある意味、情報の自由化なのであって、私としては賛成なのだが、開放された情報のダムの水を、また、下でダムを建設して、食止め様としている、大型メディアの昨今の、買収劇は、あくまでも、利権で生きていきたい彼らの脅威と、苦肉の策的な、悲壮感が見え隠れする。
ルパード・マードックは、Myspaceを自分の巨大メディアの一つにした。GoogleはYoutubeを破格の値段で買収した。しかし、一度流れ出した情報の滝は、食い止めることは容易ではない。当然、これまで、大型メディアが誘導してくれた、世間の常識、支流は、自分達の、メディアリテラシーに委ねられる。其の意味でも、個人の情報の消化能力が試されることになる。ある意味、厄介で、疲れる作業だ。果たして、今後の展開はどうなるのか?
MTVなどを持つ、Viacomは、Youtubeで、彼等が流している(結局、彼等も、垂れ流すだけで、何も努力してこなかった)PVを無断でアップロードしていると、YT側に訴訟を起こす構えだ。しかし、彼らは、PVを流すプラットフォームだけ提供して、後は、レコード会社任せ。要は、Youtubeなどの新しいインフラ(プラットフォーム)には、滅法弱い。その一方、英国国営放送(BBC)は、Youtubeに、彼らのチャンネルを作って、積極的に参加しているのは、ある意味、彼らのコンテンツに自信があるのと、半国営放送と言う性質上、ある程度、Web 2.0には、共感できる物があると考えられるのだが。
以前、欧州の利権クラブ集団(G14)については、書いたが。最近、UEFAも奥の手があるかのように、この利権集団(G14)に対抗するべく、何やら怪しい組織をUEFAの中に創設して、事実上の実権をこの組織に持たせる構えだ。この組織のメンバーの中に、欧州クラブからの相談役として、チェルシーの腕利きGM、ピーター・ケニヨンや、バルセロナのラポルタの名前が存在するのは、なんとも興味深い。要は、チェルシー側は、成金者と言う理由で、伝統と格式のある、クラブエリートとしか入れないとされる、G14に見切りをつけて、UEFA側にまわって、欧州での発言力を強めようとする狙いがありありと見える訳である。(笑)UEFA側も欧州クラブのエリートの何人かをこの組織に入れることによって、G14の結束力を弱めることができると言う、強かな思惑があるようだ。
前任が、結局この組織を創設した為に、現UEFA会長プラティ二の改革的な運営の妨げになっているのは否定できない。ある意味、UEFAも、エリートクラブの関係者を取り込んだことによって、悪質な細菌に感染したような物である。
英国の大衆紙サン紙によれば、相変わらず、ファーガソンのインタビュアーに対しての、Fワード狂は健在らしく、彼の横でカメラが回っていた、ボロのサウスゲート氏のBBCのインタビューが、カットになる程、大声で叫んでいたようです。(笑)彼が、こんなにFで反応したのは、クリスティアーノ・ロナウドくんの例の一件らしい。
今日の一言
"I don't know why. Maybe some people don't like me. Maybe I'm too good."
何故なのか僕にもわかないよ。でも、多分、僕にジェラシーを感じてるのかな。だって、僕ってイカしてるからさ。
何故貴方が絡むと、事はこんなに大袈裟になるのかの問いに。クリスティアーノ・ロナウド
オール・セインツが再結成。(笑う所です)どうやら、Take That(テイク・ザット)の再結成から、流れは、90年代の再帰に傾いているようです。恐怖だ英国音楽界。(笑う所です)彼女らと良く比較された、スパイス・ガールズは、その微塵も無く、個人で頑張っているようです。しかし、彼女ら(オール・セインツ)も、メンバーが主演する映画が、上のグループ同様に、専門家から非難の集中投下で、最も無駄な時間を費やす映画と、その有難くない汚名を頂いた訳で。その後、メンバーの亀裂が原因で、ほぼ解散状態。それぞれの地味なソロ活動に入った訳でして。日本の中古市場でも、彼女らのCDが叩き売りで放出しているのを、見ると、殆ど終わったグループだと思っていたが。
解散後も、彼女らのタブロイドネタは宝庫で、オアシスのリアムとのニコル・アップルトンとの関係は、籍を入れない関係?子供が既にいるのに。しかし、彼女、ロビー・ウィリアムスとの子を以前降ろしていると、言われているが、しかし、音楽界、好色ですな。結局、彼女らの、復帰一作目は、ルーマニアで撮影。ガールズ・アラウド ぽいっと、言われている、今風の英国のポップです。
彼女らのピークは、ディカプリオ(最近は、エコカーに乗って、環境問題に勤しんでいる)主演の映画、ザ・ビーチ(東南アジア系、ちょっと危ない人達のパーティー映画)のサントラに収録された、Pure shores辺りで、その後の、Black Coffee辺りが一番だったと記憶している、この曲は、其の頃、勢いがあった、ウォリアム・オービットの力が大きかったが。
しかし、日本のCD中古市場はどないなってるんだろうか?(笑)最近、Marionのファースト、This world and bodyをジャンクCDコーナーで、100円で購入。しかし、彼ら、英国では、再結成して、それなりの評価を受けてる昨今。このバンドの中核を担う、フィル・カニンガムにいたっては、Electronic,New Orderに参加で、ある程度知名度あるのに。〔笑)彼らは、スミスフォロワーのマンチェスターのバンドだが、不幸にも、Brit pop全盛期の時にデビューをしたために、他のバンド同様に見られたが。当時のメロディーメーカー誌の言葉を借りるなら、マンチェスター版スウェードなのであって、どちらかと言えばBrit pop色は薄い。
マッドチェスター黄金期の大御所三組内で、一番まとも(社会性)がある、御方達の、最後のアルバム。基本的に、彼等のシンボルだった、腐りかかったクリントブーンのオルガン音は影を潜めて、何故か、その後のブリットポップに繋がる仕上がりになっているような気もしないでも。彼等の活動は、そのノベルティー(Tシャツ)に頼る傾向にあったように、思えるが、メディアの使い方が上手かったのは、この大御所3組の中では、一番でしょうな。腐りかけた、日本版を300円で購入。安い買い物なのか?疑問です。因みに、ここで、まだ、素敵な牛さんTシャツは購入可能なようです。(笑)余計ですが、先程、開局した、XFM系のマンチェスター版、XFMマンチェスターの看板DJとして、招待されたクリントブーンさんは、彼の人脈(オアシスのノエルギャラガーが、彼等の裏方をやっていたのは、有名)を生かして、ノエルに電話でインタビューしたりと、マンチェスター色を濃くして、楽しくやっているそうです。因みに、このFM局の開局一曲目は、ストーン・ローゼスだったそうで。(笑)
Long-viewってバンドがいる。日本ではそんなに有名ではない。BBCのある批評家は、まるで、エンブレイスの様だと酷評していたが、何処と無く、好きなバンドである。シアトルでのレコーディングなど、ニルバーナを思わせる、グランジ系のバンドだと思ってしまった、Further のPVとは、反対に、stillでのPVは、地元マンチェスターの街の風景と、ロードムービーを思わせる、チープなPVだが、結構気に入っている。(笑)彼等は、ニューアルバムの制作に取り掛かっているとか、MYspaceでは、新曲を披露している。Long-viewと言う名前どうり、地道にやって欲しい。こんな、急ぎ過ぎる、音楽界の中では、なかなか難しいが。